「連立政権はいつから?」
「なぜ連立政権は終了したの?」
「連立解消による自民党への影響は?」
自民党と公明党による連立政権。与党として、この二党が手を取り、政権を握ってきたことは皆さんもご存じかと思います。
ただ、「なぜ二つの党が手を取り合っているのか」「たくさんの党がある中で自民公明の二党だったのか」等、詳しく知っている人は多くないと思います。
かく言う私もその一人でした。
昨今、若者の政治への関心の低さが嘆かれていましたが、先の参議院選では「自民党の裏金問題」等もあり、現在の政権に懐疑的な目を持つたくさんの方が投票へ出向き、様々な価値観の中で投票を行ったと思います。
その結果、与党である自民公明の議席数が衆参で過半数を割り込み、今まさに国政の転換期ともいえる時代が到来しています。
そんなタイミングでの石破首相の辞任&高市新総裁の誕生。そして極めつけに自民公明の連立終了報道。
このように様々なことが一度に起こっている今だからこそ、この記事をお読みいただき、連立政権が終わることによりどのように政界が動くのか、どんな未来が見えてくるのかをぜひ、ご理解いただきたく思います。
そもそも連立政権とは?
「連立」とは、複数の政党が協力して一つの政権をつくることを言います。一つの政党では衆参両院で過半数の議席を確保できない場合や、より安定的な政権運営を目指す場合に行われます。
そもそも国会での議決は大の大人が多数決を取って決まっていますから、より仲間が多いほうが自分たちの通したい政策が通りやすくなるので一緒に手を組むわけですね。
なぜ連立政権は終了したのか?
自民党と公明党は今から26年前の小渕恵三政権時に連立政権を開始しました。
その経緯としては、自民党が単独で過半数を確保できない局面を補う戦略と、公明党が国政に影響力を持ちたいという双方の利害が一致したことがあります。また、公明党が持つ組織票(創価学会を支持母体とする選挙支援)は、自民党にとって選挙戦を戦う上で大きな強みとなってきました。一方で、政策調整の過程では自民党が譲歩を迫られることも少なくなく、教育、福祉、外交・安全保障などの分野で双方の主張をすり合わせながら政権運営を行ってきました。
それでは、これまで安定的に連立政権を進めてきた自民公明両党がなぜ、連立解消となってしまったのかについてを記します。
やはり「政治とカネ」の問題についてが連立解消の理由として挙げられました。
公明党としては、「政治不信の払拭」を最優先に考え、裏金の温床となりかねない不透明な資金の流れを断ち、国民の信頼を回復することを目的に、企業や団体からの献金の受け皿を、透明性の高い政党本部や都道府県連などに限定し、政治家個人につながるような資金の流れを厳しく制限する案を求めました。
対して、自民党の返答は
企業・団体献金は、全国各地で活動する自民党の地方組織や選挙区支部にとって、重要な活動資金となっているのが実情です。もし公明党の案をそのまま受け入れれば、「地方の政治活動が立ち行かなくなり、組織が弱体化してしまう」という強い懸念があり、難色を示しました。
これについて、最終的に公明党は
自民党の回答は不十分であり、国民の信頼を得られるものではない」と判断し、連立関係の解消に至ったわけです。
連立解消による自民党への影響は?
まず1つ目は政策決定までのスピードが恐ろしく鈍化することが考えられます。
これまで自民公明で衆参両院の過半数の議席を確保していたため、議決まで持っていけていましたが、連立解消により自民党とその他の賛成してくれる政党がある政策を見込んで決議していく必要がありいます。そのため、野党の動向を常に気にしながらの政権運営をしなければならなくなりました。
2つ目は次期選挙への影響です。
これまで2党で過半数を狙っていた議席を自民党は単独で目指さざるを得なくなりました。
公明党には創価学会という大きな後ろ盾がありましたが、その支持も受けることができなくなるため、大変苦戦を強いられることになるでしょう。
政権交代もあり得ますね。
最後に3つ目は、現在一番注目度の高い、次期首相についてです。
当然のように今までは自民公明で自民党総裁にすべての票を集めていたので「総裁=首相」となっていましたが、今回からは公明党も代表の斉藤鉄夫議員に投票する意向を示しています。そのため、すんなり決まらず、決選投票にもつれる異例の事態にもなりえるということです。
まとめ
これまで26年という戦後では最長の連立政権を実現させてきた自民公明両党。
しかし、今回「政治とカネ」の問題を焦点に連立解消まで進んでしまいました。
私たちの生活にはどのような影響があるのかというと…
やはり、政策決定が容易ではなくなったことに挙げられます。消費税や減税、移民問題等、様々な問題を抱えている昨今ですが、なかなか政策が通らず、国民への負担ばかりが増す可能性も考えられます。
政治家の皆さんには「誰のための政治なのか」を常に念頭に置き、立案、決議をしてもらいたいものですね。

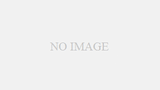
コメント